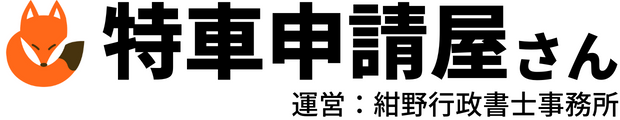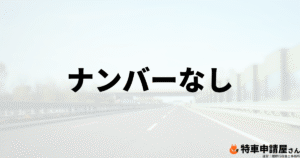これだけ知っておこう!特殊車両通行許可申請の基礎知識
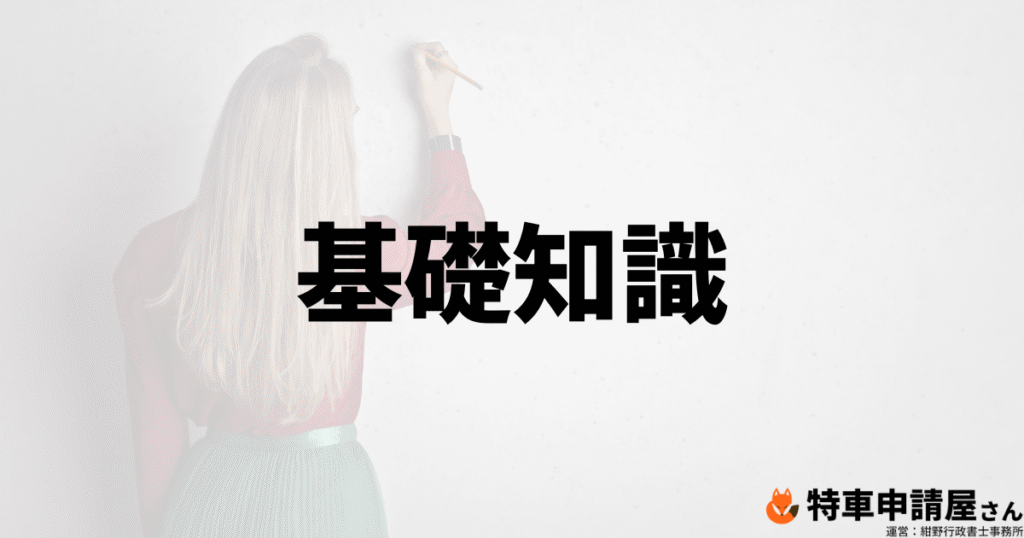
東京都武蔵村山市の特車申請屋さん(運営:紺野行政書士事務所)です。
実は、トレーラーやダンプのような大きく重いクルマは普通のクルマとは異なり、いつでもどこでも自由に走れるわけではありません。
公道を走るためには、車両と経路ごとに申請して、許可証を携帯しなければならないのです。
この制度を特殊車両通行許可と呼びます。
道路の保全や交通の安全のため、年々、取締りは厳しくなっており、許可件数は増えているものの、まだまだ無許可の車両も多いと思われますが、事業者が安全に法令を守って運行するためには重要な、知る人ぞ知る許可です。
この記事では、これだけは知っておきたいという特殊車両通行許可の基礎知識を専門の行政書士がわかりやすく解説します。
特殊車両とは
特殊車両とは、一般の道路を通行するために特別な許可が必要な大型や重量の車両を指します。
特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められており、この許可のことを特殊車両通行許可といいます。
特殊車両は原則、道路を走ることは禁止されているため、それを例外的に解除するための許可となります。
この申請には、多くの書類や手続きが必要ですが、企業が特殊車両を安全かつ法的に運行するためには、この許可は欠かせません。
特殊車両通行許可について詳しい解説はこちら▼
全体像がわかる!特殊車両通行許可の申請から許可までの流れをわかりやすく解説
特殊車両の基準とは
車両のサイズや重さがある基準を超えると特殊車両に該当します。
この基準のことを一般的制限値と呼びますが、以下の表の数値をひとつでも超えれば特殊車両です。
特殊車両通行許可は、連結して積載した最終形態で審査されますので、実際に公道を走行する最終形態で基準値を超えてるか確認してください。
※基本的に、幅、長さ、高さ、総重量がチェックできればOKです。
| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
|---|---|
| 幅 | 2.5メートル |
| 長 さ | 12.0メートル |
| 高 さ | 3.8メートル |
| 総重量 | 20.0トン |
| 軸重 | 10.0トン |
| 隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 |
| 輪荷重 | 5.0トン |
| 最小回転半径 | 12.0メートル |
申請先はどこ?
出発地点から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
また、国道と県道を通行するときのように、申請経路に2つ以上の道路管理者がいるときには、どちらか1つの上位の道路管理者に申請します。
実際は、ほとんどの場合、複数の道路管理者をまたがりますので国道事務所に申請することが多いと思います。
申請書の提出方法は?
インターネットを利用して申請する「オンライン申請」と、申請窓口へ出向いて書類を提出する方法があります。
オンライン申請では、原則窓口へ出向く必要が無くなるなど、手続きが大幅に簡素化されます。
現在はほとんどの方がオンライン申請をしていますし、行政庁もそれを推奨しています。
窓口申請にメリットはないので、申請方法としては、基本的にオンライン申請となるでしょう。
審査期間はどれくらい?
申請されてから審査が終了するまでを標準処理期間と呼び、以下の通りです。
・新規申請および変更申請の場合は、3週間
・更新申請の場合は、2週間
注意点として、この標準処理期間は、申請経路が収録道路(行政庁で道路情報を保有済)で完結している場合の審査期間です。
未収録道路が含まれている場合はこの限りではありませんし、実際には、未収録道路が含まれていることが多いため、目安と考えるのがよいでしょう。
経験上、審査期間は通常1~2ヶ月、長いときで3~4ヶ月かかります。
約1週間で審査が終了することもありますが、これは申請経路が収録道路で完結するときに限られます。
申請経路が収録道路で完結するかどうかは実際に経路作成しないとわからないため、申請前の段階で判断はできませんが、申請書が完成した段階であればわかりますので、申請した際に審査にどれくらいの期間がかかるかはある程度の予測ができます。
審査期間について詳しい解説はこちら▼
1週間で許可は出るのか【最短3日】【特車申請】【間に合わない】
許可証の有効期間
許可証には有効期間があり、たいてい、2年間か1年間です。
有効期間内は何回でも許可された経路は走れますが、有効期間には気をつけましょう。
有効期間を過ぎた許可証は携帯していても無許可と同じ扱いで違反となります。
許可証の表紙に赤いマーカーで車番と有効期間を目立つように書いてもよいでしょう。
有効期間切れの許可証を使った場合の罰則について詳しい記事はこちら▼
知らないと損をする?特殊車両通行許可に関する罰則と取締り
記事全体のまとめ
この記事では、これだけ知っておきたいという特殊車両通行許可の基礎知識を解説しました。
現在、特殊車両を扱っている方やこれから申請を検討している方の参考になれば幸いです。
特殊車両通行許可申請は事業者が安全かつ法令を守って運行するために必要な手続きですが、非常に複雑で手間がかかります。
道路法、車両制限令、道路交通法などの法令知識が必要な上、実務処理や役所対応のノウハウも求められます。
さらに、法令や制度は常に変わるため、その都度対応が必要です。
行政書士に特殊車両通行許可申請を任せることで、通行許可の取得後も専門的な視点から相談に乗ることができます。
特殊車両通行許可に関することでお困りの方は、専門家である行政書士にご相談ください。